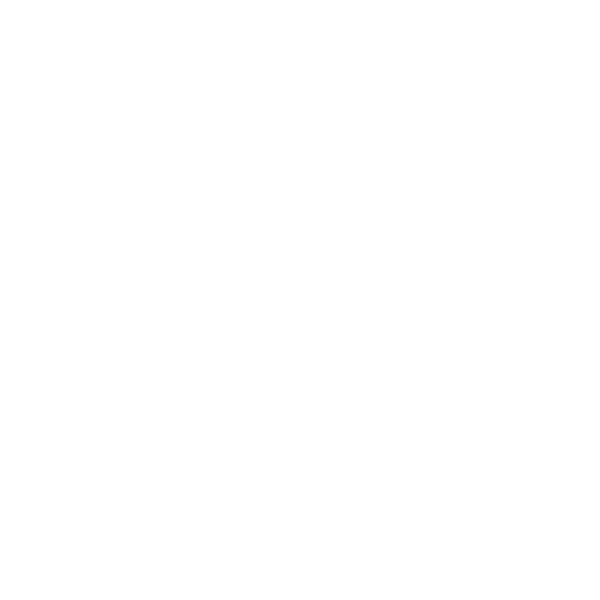すみだ川アートラウンド・ハブ
対話と支え合いの評価手法
ピアレビュー実践報告会ーゆるやかな関係がつなぐ「場・ひと・こと」を語り合うー
開催レポート
2025年1月実施:すみだ川アートラウンド・ハブ
開催レポート
テキスト:森隆一郎(すみだ川アートラウンド・ハブ ディレクター)
開催概要
日時:2025年1月18日(土)14:00-16:00(開場13:30)
会場:東京藝術大学 千住キャンパス スタジオA(東京都足立区千住1-25-1)
登壇者:
<ピアレビュー実施メンバー>
江間みずき(ハタメキ主宰/俳優/着付師)
齊藤英子(OGU MAG+主宰/アート・映像コーディネーター)
<ゲスト>
藤浩志(美術家/株式会社 藤スタジオ代表/秋田公立美術大学教授)
大内伸輔(東京藝術大学 特任准教授)
<すみだ川アートラウンド>
熊倉純子(すみだ川アートラウンド プロデューサー/東京藝術大学 教授)
森隆一郎(すみだ川アートラウンド・ハブ ディレクター/合同会社渚と 代表社員)
これまでの流れ
東京の文化を語るとき、隅田川沿いの雰囲気をうまく言い表せないかなと感じつづけてきました。
いわゆる東京の下町文化ともいえるのですが、やや使い古されている感じもあって、新たな活動が生まれるような言葉と出合えないかなと。人と人が近くて、気軽でかっこつけなくてもいい。西側の所謂トーキョーの雰囲気とは違うのだけど、だからといって古くさいわけではなく、いや、どちらかというと先端の芸術や技術が集まっている面もあると感じます。しかも、その担い手たちは近所に住んでいて、観光で訪れる人には分かりづらいかもしれないけれど、住んでみると、そういう古いものと新しいものが混在している良さに気づいてしまう感覚。
そんな地域の有様を「隅田川文化圏」と名付けてみて、その文化圏を支えるようなことができないだろうか。そんな漠然とした思いがあり、この一連の事業に携わってきました。一連の事業というのは、2019から2021年度まで行った「Meetingアラスミ!」というプロジェクトと、この「すみだ川アートラウンド」です。いずれも東京藝術大学が文化庁から助成をいただいて進めてきました。「Meetingアラスミ!」については、こちらに詳しいのですが、簡単に書くと、隅田川沿いの3つの自治体(足立区、墨田区、台東区)の文化政策を連携させ、地域における小さなアーツカウンシル(中間支援組織)を作って、地域の文化的な取り組みを支えられないだろうか、という実験でした。
そんな実験を受けて、この3年間(2022〜2024年度)は、対象エリアも7区(足立区、荒川区、北区、江東区、墨田区、台東区、中央区)に広げ、民間の小さな文化的拠点・活動に着目し、ネットワークの基礎体力づくりのような事業を行い、これまで8つの団体に参加してもらいました(https://artround.geidai.ac.jp/hub/)。
このすみだ川アートラウンド・ハブでは、地域で活動する小さな文化拠点・団体を対象に、それぞれの活動について共有してみたり、ネットワークを促してみたりして、より現場に近いところで、中間的支援のあり方を模索してきました。
ピアレビューについて
ピアレビューについて
当事者にしてみれば、ちょっとお節介とも感じられるかもしれませんが、この事業で中間支援的な手法として取り上げたのが、ピアレビューです。ピアレビューとは、タイトルにも付けましたが「対話と支え合いの評価手法」と言われています。具体的には、似た専門性や知識、技術、経験を持つ他者同士(ピア)が互いの活動を見たり体験したりして、そこで感じたことや気づいたことを共有(レビュー)することで、互いに現状の課題を見つけ、自分たちの活動を改善していく手法です。さらに、今回のピアレビューは、互いの交流のきっかけにもなったようで、私たちが当初想定していたような、隅田川文化圏における地域の繋がりが生まれたのではないかと考えています。
報告会の様子
今回、このプロジェクトに参加してくださったのは、荒川区にあるOGU MAG+というギャラリー・カフェと江東区にあるハタメキという喫茶店です。2つの場所のことをギャラリー・カフェや喫茶店と紹介しましたが、この2箇所の活動はそこにとどまらない可能性を秘めていますし、幅の広さを持っています。

左:OGU MAG+ 右:ハタメキ
それぞれ運営しているのは地元の人で、個人の想いから出発しつつ、周りの人たちも仲間にしながら、地域を巻き込んでいくような場所。この報告会では、ピアレビューの再現的に、互いの場のことを伺っていきました。
Q:各スペースを始めたきっかけは?
江間みずきさん(ハタメキ):地元深川の生まれ育ちで、もともとこの長屋に憧れを持っていたところに空きが出て、地域の人が気軽に文化との接点がつくれる場所を作りたいと思い、そこから喫茶店という形になった。
齊藤英子さん(OGU MAG+):スペースを始めるときに学生時代に留学していたロンドンの下町に点在するギャラリーのイメージがあり、自分の暮らす街でもやってみようと思った。

ハタメキでは、俳優やバレリーナなど個性的なスタッフが店頭に立っている
Q:スペースの紹介
江間さん(ハタメキ):自然発生的に始まったイベントが多い、特に「石フェス」は力が入っているが、いろいろな人が自分のスキなことを追求できる場所。
齊藤さん(OGU MAG+):近隣にアトリエなども多く、ものづくりを地域の人が身近に感じられる場所として、展示及びワークショップなどを行っている。また、カフェに入ってきたことをきっかけに展示を見るということも起こっている。2階はレジデンスになっていて、今は1〜2年の長期で滞在する方が多い。1階での主催事業や貸ギャラリーのマネジメントで手一杯になるから、レジデンスは長期の方とじっくり関係が作れてありがたいと思っている。また、ギャラリーを貸し出すときにも、1時間程度の面談をして、人となりや想いのズレが無いかなどを確認している。
Q:スペースの継続性:収入源について
江間さん(ハタメキ):収入は、ほぼカフェの売上げでまかなっている。
齊藤さん(OGU MAG+):カフェとギャラリーのレンタル代で大体半々、レジデンスは大家が自分の親なので、家賃は親へ渡すが、管理費程度を貰っている。

左:ハタメキの江間さん 右:OGU MAG+の齊藤さん