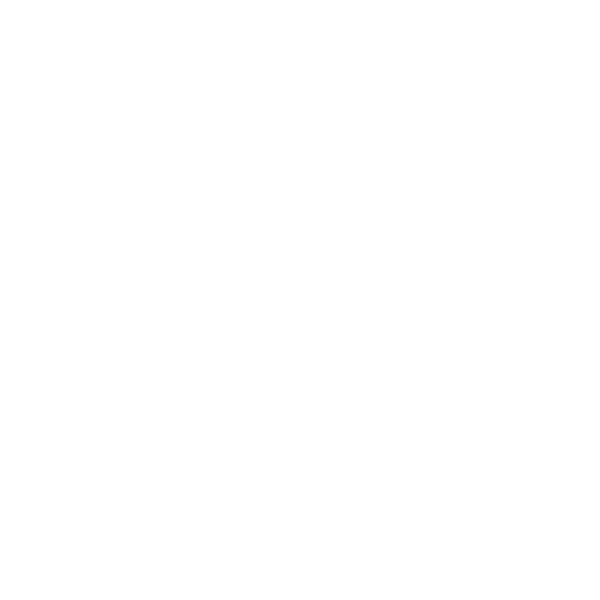ゲストを交えたディスカッション
ここで、ゲストの大内伸輔さん(東京藝術大学特任准教授)、藤浩志さん(美術家)が合流します。まずは、自己紹介的なコメントと今回ピアレビューを行った2箇所についての感想をお願いしました。
大内さん
「前職のアーツカウンシル東京で場作りに関わってきた。担当していた事業「東京アートポイント計画」で、都内のアートプロジェクトを行うアートNPOなどのピアレビューやネットワークづくりに取り組んできた。公的な事業なので、団体は卒業していくのだが、その後も各団体が孤独にならないようなネットワーキングなども行っていた」
藤さん
「美術作家としては、まだデビューしていないような感じ(笑)だが、自分では、作る場や関係、仕組み、ツールなどを試してきたと感じている。福岡県糸島にある自宅や、鹿児島の実家で様々な実験を行ってきた。空き家をいじるのが好きで、大阪の此花区では「此花メヂア」を始め、いろんなアーティストが住んできた。今では此花区に100名以上のアーティストが暮らしていると思う。また、ここ10年ほど(秋田公立美術大学の教授として)秋田に住んでいて、空き家を見つけると自分で改装しながら住み、それを若いアーティストに貸し、彼ら彼女らがシェアハウスやシェアアトリエにするというような活動をしている。11年間で13箇所借りた。いろんなことをやっていると、いろんな人と関係ができていく。何かをやると、街に連鎖していく。ハタメキとOGU MAG+の2箇所は、新しいコミュニティや成功例を作っていくための拠点でもあると感じた。創る人に対して、安心できる場所となっていて、それが地域にもつながって行っていると感じた」

左:大内さん 右:藤さん
自己紹介と感想の共有のあと、齊藤さんと江間さんがそれぞれ、ゲストの二人に質問していきます。
仕組み作りとは?
齊藤さん(OGU MAG+)
「まだできていないのは仕組み作り。自分がいなくてもできるような仕組み作りはどうやるのか?」
藤さん
「その場に応じてそこに居る人とできることから考えるしかない。誰かが登場することを待つ。ただ、貸しギャラリーだけでなく、主催事業を行うことも大事で、場のあり方を示していく。餌をまくというか。また、街を見て歩くのも大事。街の関心が少ないと感じるときは、まず自分自身が街に関心を持つことから始める」
大内さん
「出会いの確率が高い場所だと思う。そういう出会った人の中から、この部分は任せてみよう、と展開する可能性もある」
発信の方法について
江間さん(ハタメキ)
「発信の仕方を聞きたい」
大内さん
「貸しギャラリーとして壁を貸すことを発信するのではなく、やっていることを紹介し、いろんなことが起こっているという状況を発信していくと良いのではないか」
藤さん
「これから何をやるかよりも、なにをやったかというレビューとかレポートをしっかりと発信・蓄積していくことが大事。また、空間の意味などを発信すること。他者に紹介して貰うようなことも面白いと思う。未来ではなく過去を記述していくこと。伝えるではなく、つなげていくことが大切」
大内さん
「レポートを自分で書くことで気づくこともあるし、人に書いて貰うことで気づくこと(このピアレビューのように)もある。気づき合いを言葉にして残していく」
場の手放し方
場の手放し方
齊藤さん(OGU MAG+)
「どのくらいのタイミングで手放すのか?」
藤さん
「ケースバイケースではあるが、(手放すと言うより、もともと)自分はどちらかというと空間や空気を作るのが好き。仕組み作りの話でいくと、場としてのOS(基本的な仕組み)を作る。アプリケーション(イベントとか展示とか)が動くための大きな仕組みに興味があって取り組んできた。企画を作るのではなくいろんな企画が動ける場を作ること。そういうことをやってきた気がする。MacOSやWindowsOSが出てきたときに感動した。パソコンに何でも接続できるしいろんなことができる。それを、文化施設・拠点にも導入してきた」
森
「藤さんは古いと仰るが、まだまだやれていない場や文化施設の方が多いと思う」
藤さん
「ハード/ソフトではなく、OSが大事」
大内さん
「企画などを委ねていく仕組みがあると、頼れることが増えていく。少し大変かもしれないが、そこをどういう場にしていきたいかというディレクションがしっかりしていれば、賛同した人たちが集まり、徐々にその場所のカラーができてくると思う」
藤さん
「(ハタメキの活動リスト(下図)を見ながら)これって部活だと思う。この場所は部室になるなと感じた。なにがその場にあるのか(ツール)が大事で、部活にはそれぞれのツールがある。ツールの周りに仕組みが発生する。活動を分割していき、それぞれの現場を任せていくようなイメージ」
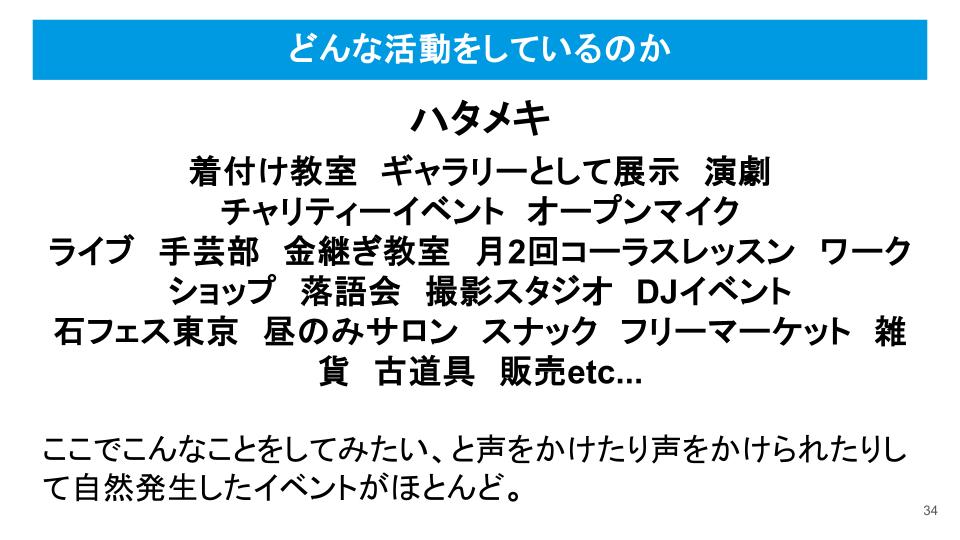
ハタメキの活動内容
大内さん
「例えば、ただ店員としていてもらうだけでなく、少しその人の得意技を見せて貰うとか。そういった小さな工夫でも場の個性は際立つし、なおかつ本人の活動にも影響するかもしれない」
縁を大事にして、新しい価値観を提示していく場所として
締めには、熊倉純子さんから「行き当たりばったりでよい」という、場のあり方に対して背中を押すようなコメントがありました。
熊倉さん
「街の中に、民間の顔が見える文化的な場所があるのは、改めて重要なことだと感じた。公共のものは、それはそれで意味があるが、みんなのものになるのに何十年もかかる場合がある。一方、「街の人が気軽に立ち寄れる場」を実現したくて喫茶店から始めるとか、身近な存在でオーナーに相談すれば「審査」があるわけでなく、活動を始められるとか、そういう場が暮らしの近くにあるべき。なぜなら、人は断片的な文化の集合体でできあがっている。ここ50年くらい消費者としか生かされてこなかった人たちに対して、商業主義とは違う価値観の場があることが大事。また、行き当たりばったりも重要で、藤さんもビジョンとかが嫌いと言っていたが、行政のお金でやっているわけではないのだから、縁がつながっていくことを重視していく、それでいいのではないか。お二人とも、縁ができることを丁寧に考えていて、お二人の周りにネットワークができていると感じた。新しい人がやってきたときに、面白そうだからやってみたら、というのが藤さんのスタイルだと思うが、お二人それぞれのスタンスでやっていけばいいのではないか、こうすべきというのはないのではと感じる。また、お二人が現代アートなどの間口の狭いところにこだわっていない点も良いところだと思う」
活動が肯定され、経験に裏付けされた考え方なども共有され、お二人にとってとても実りのある会になったようです。江間さんは、後日、「皆さんにこれで良いのだという勇気づけられる言葉をもらえて気持ちが楽になりました」と仰っていました。

左:熊倉さん 右:森さん
質疑応答
〔質問1〕「街の人とのコミュニケーションで心がけていることはあるか?」
齊藤さんは、店主であるだけでなく、地元に長く住む住人、良き隣人であるため、挨拶を大切にしていると話し、江間さんは、カフェにこもりがちになるため、ピアレビューをきっかけに、自分が店にいる曜日を決め、その日以外は外に出て街の変化を感じるよう意識していると返しました。ゲストの大内さんは、場にいることと地域に出て行くことのバランスを考えることが大切だと指摘し、藤さんは、アートプロジェクトの基本は挨拶と掃除であり、熱意を持って活動すると周囲にも影響を与えると話しました。
〔質問2〕「街の『会所』のような場だと感じたが、場所に対する思いを教えてほしい」
齊藤さんは、夫や家族の協力でカフェを運営し、地域の人々が集まる温かい場所になったと話し、江間さんは、清澄白河には土日に多くの人が訪れるため、平日は地域の人々と積極的に交流し公民館のように使ってもらえるよう工夫していると語りました。
ちなみに「会所」というのは、室町時代から江戸時代にかけて続いてきた場で、例えば、そこで連歌会が行われるときは、参加する人の身分は問われず、自由に表現できたということです。まさに、お二方の運営する場所からは、「会所」のような雰囲気が感じられました。
結びに
江間さんは、ピアレビューをきっかけに多くのことが前に進み、すでに店内改装にも着手しているそうです。今後もこのつながりを大切にしていきたいと話し、齊藤さんは、新たなつながりができたことに感謝しており、特に江間さんの行動力や柔軟な姿勢に共感を覚えたとのことで、今後の展開についても相談に乗ってもらえたらありがたいと結びました。ゲストの大内さんは、今回の経験が多くの学びにつながったのではないかと話し、不安もあるかもしれないが自信を持って続けてほしいとエールを送り、二人の活動が周囲に影響を与え、新たな動きを生み出す可能性についても指摘しました。同じくゲストの藤さんは、地域活性化という言葉よりも「発酵化」や「豊穣化」のほうがしっくりくると話し、発酵によってじんわりと温かくなるように、地域にも発酵を促すような土壌づくりが必要だと語りました。そして、この地域には良質な菌が多く、すでに発酵が始まっているように感じているということでした。
最後に、熊倉さんは、行政区分を超え、小さな民間の動きがつながる視点をもって3年間取り組み、大学が地域のお世話を焼くことも悪くないのではないかと考えてきたと結びました。
(参考:小さな文化拠点を研究した論文)
「現代日本における小規模民間型アートスペース《micro art space》の流転 : 2000年以降設立の事例から、主宰者たちの眼差しを中心に」

熊倉純子・槇原彩監修(2020)『アートプロジェクトのピアレビュー 対話と支え合いの評価手法』水曜社。
所感
あらためて、何故こんなことを試してきたのかについて整理してみたいと思います。
「この街、なんかいいよね」という思いを共有したい。それが、地域の振興につながったり、住んでいる人たちのシビックプライドに結びついたりすると良いな、と考えてきました。そのために大事なのは、やはり地域の文化的な側面だと思います。交通の便の良さや家賃の価格などの利便性だけでは、人の感性には訴えられないのだと思います。そこで生まれ育っていない人たちが、なぜその街や地域を愛せるかというと、自然の景観に惹かれた場合を除くと、地域の文化が好きだからということになるのではないでしょうか。
もちろん、「文化」の概念は幅広く、広辞苑には「文化」は「自然」の対概念とあります。つまり、人間が作ってきたあらゆるモノやコトは「文化」といえるのでしょう。そのくらい広く「文化」を捉えた上で、街を眺めてみると、古くは祭りや伝統行事があって、子どもの頃は学校行事があり、だれかと共になにかをする機会がありました。
では、地域の伝統行事に参加していなくて、その地域で育ってもいない大人たちは、どうやって地域とつながっていくのでしょう。もちろん、誰とも深く付き合わずに孤独を謳歌できるのも都会の良いところですが、街や地域との接点を求めたいと感じるときに、地域の文化拠点は応えてくれるでしょうか。熊倉さんも発言されていたとおり、公立の文化施設は、その部分の対応がうまくない場合もあると感じます。一方で、今回ピアレビューに参加してくれたOGU MAG+やハタメキのような場所は、いっぺんに何十人もの人には対応できないでしょうが、一人ひとりと丁寧に向き合ってくれると思います。
この活動に6年間携わってきて、改めて街に必要なのは、こういうきめ細かな動きが得意な小さな文化的拠点が多くあることなのではないかと感じています。そこは、個人の思いが詰まった民間の場所で、人の多様なあり方に寛容であり、自分のスキなことに没頭できて、仲間もできていくような場所。ただ、そういう場を創っている人は、孤独を感じ、ネットワークを求めているという側面もありました。街/地域としては、そういう場に今後も続いてほしいし、発展してほしい。そこで、私たちが大学という立場を生かして、その地域に対して、ややお節介かとも思えるようなアクションを試してきました。
すみだ川アートラウンド・ハブは、このような小さな活動をエンパワメントする役割を、地域の大学が担ってみた取り組みです。この役割は、中間支援的なNPOが担っても良いかもしれません。大事なのは、地域で小さなクリエイティブが地産地消していき、住んでいる人が「街の推し活」的に街を自慢できるような場を担っている人たちの背中を押していくこと。こんなことが少しずつ起こっていくことが「この街、なんかいいよね」という気持ちにつながっていくのではないかと考えています。そういうことが積み重なり、街の独自性が育まれていくのではないでしょうか。
この活動は、これで一端の幕を引きますが、地域にとってとても大事なことだと感じますし、このような活動を担ってくれる組織ともまだ出合えていないので、私たちで、次のステップも考えていきたいと思います。
森隆一郎
すみだ川アートラウンド・ハブ ディレクター
「すみだ川アートラウンド・ハブ」開催概要
講座名:対話と支え合いの評価手法 ピアレビュー実践報告会ーゆるやかな関係がつなぐ「場・ひと・こと」を語り合うー
日時:2025年1月18日(土)14:00-16:00(開場13:30)
会場:東京藝術大学 千住キャンパス スタジオA(東京都足立区千住1-25-1)
登壇者:江間みずき(ハタメキ主宰/俳優/着付師)、齊藤英子(OGU MAG+主宰/アート・映像コーディネーター)、藤浩志(美術家/株式会社 藤スタジオ代表/秋田公立美術大学教授)、大内伸輔(東京藝術大学 特任准教授)、熊倉純子(すみだ川アートラウンド プロデューサー/東京藝術大学 教授)、森隆一郎(すみだ川アートラウンド・ハブ ディレクター/合同会社渚と 代表社員)
講座運営:岡田千絵、吉田武司 ※敬称略
講座記録撮影:中川周