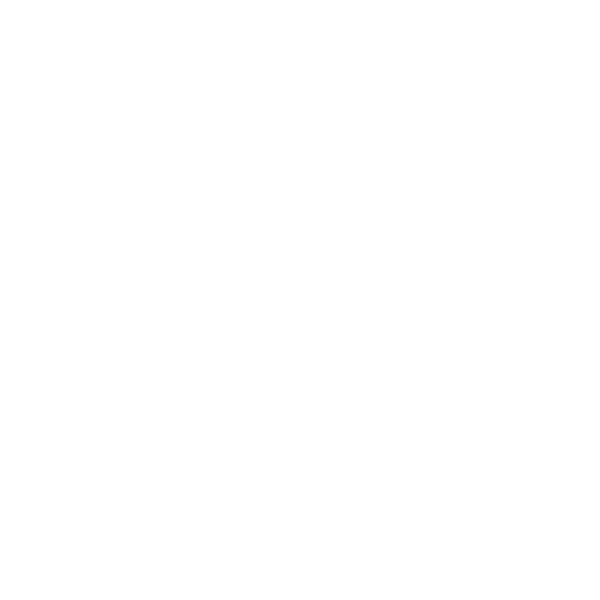すみだ川アートラウンド・ハブ
流域で活動する官/民の交流の場 開催レポート

『隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方』とは
東京都建設局河川部が2023年6月に公表した「隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方」(http://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000063618.pdf)では、水辺の整備・利活用を促進するために、多様な主体をつなぐ中間支援組織の構築が提言されました。中間支援組織は、「マネジメント(水辺運営)」「コーディネート(関係者調整)」「ポータルサイト(情報窓口)」という複合的な機能を提供するという構想が描かれました。
東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科が隅田川流域に関わる官民のネットワーク構築に取り組む事業「すみだ川アートラウンド」では、民間視点を踏まえた「中間支援組織」についての検討会を実施し、具現化に向けたアイディアや課題の顕在化を行いました。
東京都河川部とパブリックスペースの利活用におけるトップランナーで構成されるボードメンバーが集まり、対話することで、どのような将来像が描かれたのでしょうか。2025/3/2(日)に開催された本イベントでは、隅田川を航行する船上を舞台にして、シンポジウム形式で検討会での議論内容を報告するとともに、参加者による隅田川流域の将来像を描くワークショップを行いました。
登壇者・ボードメンバー:佐藤留美氏(NPO法人 NPO birth 事務局長/ GreenConnectionTokyo 代表理事)、倉持美冴氏(取手アートプロジェクト 事務局長)、大内伸輔氏(取手アートプロジェクト/東京藝術大学)、関谷進吾氏(三菱地所株式会社)、安藤哲也氏(柏アーバンデザインセンター 副センター長)、岩本唯史氏(株式会社水辺総研 代表取締役)、飯石藍氏(公共R不動産)、清宮陵一氏(NPO法人トッピングイースト 理事長)
検討会参加者:東京都建設局河川部、国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所、墨田区 文化芸術振興課、東武鉄道株式会社 など
本レポートでは、以下の内容で検討会とワークショップの内容をご報告します。
- 第1回目から第4回目のトークテーマおよび船上での振り返り内容のご紹介
- ワークショップ参加者のアイディアについて
- 隅田川の将来に向けた想像の広がり
第1回目:佐藤留美氏 × 飯石藍氏 @ 東京藝術大学千住キャンパス
NPO法人NPO birthの佐藤留美氏は、日本にNPO法が存在していなかった1997年から、NPOの先進地アメリカで佐藤氏が学んだ中間支援の取組を日本に持ち帰り実践してこられました。第1回目の検討会では、25年を超える佐藤氏の経験の中で培われた理念から中間支援の具体的な手法まで、幅広いお話を伺うことができました。
ボードメンバーによる議論では、「中間支援組織の役割について」「中間支援とボランティアの違いについて」「ボランティアの集め方について」など、深く掘り下げた質疑が飛び交いました。
特に盛り上がった「中間支援組織の役割について」の議論では、中間支援組織は「いろんなもの(人や協賛金)を集めてくる」ことが役割だという意見が出ました。呼応して、「地域の人脈、人の水脈の掘り起こしから始める」ことが重要だという指摘がなされました。
「人の水脈の掘り起こし」は、「話しながら地域の顔になっていく。話しながら地域のモチベーションを上げていく」というスキルが必要で、簡単なように見えて、実は難しいことです。「足で稼ぐ」、「最初の数年間は耕し続ける」ことの重要性についても指摘がありました。
また、行政と地域では課題感が異なるという指摘や、「自分1人ではできなかったが、みんなでやることで目標に達した」という経験を作り出すのが中間支援の役割だという意見が出されました。

第2回目:倉持美冴氏 × 大内伸輔氏 @ NPO法人トッピングイースト
取手アートプロジェクト(TAP=Toride Art Project)は、1999年より市民と取手市、東京藝術大学の三者が共同でおこなっているアートプロジェクトであり、初めの12年間におけるフェスティバル型の取組と、通年プログラムへのシフト後のコアプログラム《アートのある団地》《半農半芸》《藝大食堂》などの取組を行ってきました。第2回目の検討会では、取手アートプロジェクトの倉持美冴氏・大内伸輔氏から、取手アートプロジェクトの1999年からの歩みと今後の展望を伺いました。
ボードメンバーによる議論では、「アート」と一般的な「市民」の間の乖離を上手く繋げる中間支援のスキルについての質問や、取手アートプロジェクトの結果として市にどのような影響があったかという質問が飛び交いました。具体的な影響として、例えば、テナントが撤退した取手駅ビルの4Fに文化交流施設である《たいけん美じゅつ場 VIVA》を設置したことで、この場所に様々な学校の高校生が放課後に集まるようになってきたそうです。
中間支援によるアウトプットの評価の難しさについても言及がありました。「行政の予算や人事の考え方とはタイムスパンが異なり、担当が2年で変わる異動体制であれば、取組を開始した担当者の間に成果は出ない」という現実に即した指摘があり、行政・民間双方の担当者が、「成果を出せることを信じる」重要性について語られました。

第3回目:関谷進吾氏 × 清宮陵一氏 @ 汐浜テラス
タイムズスクエアやユニオンスクエアといったニューヨークの有名な公共空間は、法人格を持った非営利団体であるBID(Business Improvement District)によって運営されてきました。第3回目は、三菱地所株式会社の関谷進吾氏にお越しいただき、ニューヨークのBIDやコミュニティボードの仕組みについて伺いました。
ボードメンバーによる議論では、特にBIDの構成メンバーは「定められた役割を果たすことができるか」によって選ばれるという点に注目が集まりました。意思決定(代表)、渉外・調査(副代表)、経済開発、マーケティング・イベント、運用という役割の5人組に、金融の仕組みが分かる人を加えると、水辺の運営をするBIDのような組織が日本でも考えられるのではないか、などと想像が膨らむセッションとなりました。BIDは若手がOJTで学ぶ場となっており、BIDを繋ぐ団体や、学び合う仕組みがある、という点も興味深いお話でした。一方でコミュニティボードは各地区で51名のメンバーが選ばれる組織で、BIDなどがエリア単位で地域にリーチしたい場合のコンタクト先となっています。ポートランドのネイバーフッドアソシエーションとの比較が行われ、議論は盛り上がりを見せました。
ニューヨークの公共空間活用が『PlaNYC』の策定をきっかけに盛り上がりを見せたように、『隅田川等における未来に向けた水辺整備のあり方』がきっかけになれるのではないかという期待の声がありました。また最後には、行政に期待するだけでなく、ビジョンを持ったリーダーが物事を動かしていくことが重要なのではないか、と今後の進め方のポイントが示唆されました。

第4回目:安藤哲也氏 × 岩本唯史氏 @ 汐浜テラス
柏アーバンデザインセンター(UDC2)は公・民・学が三位一体となって柏駅周辺のまちづくりを推進する課題解決型のまちづくり拠点として、「グランドデザイン」の策定や、市民参加の実行委員形式で運営するストリートパーティの実施を行ってきました。第4回目は、UDC2副センター長の安藤哲也氏をお招きして、UDC2の活動や、地域や行政との向き合い方について伺いました。
ボードメンバーによる議論では、市民の巻き込み方や行政との付き合い方について多くの質問が挙がりました。「市民の活動を自走させるために何をすればよいのか」という質問に対して、「ハード面・ソフト面双方で魅力的な都市空間にしていくために、すぐに自走させようとするのではなく、(行政や中間支援組織が)事業者や市民に伴走することは必要」という回答がありました。特にUDC2の理念や方針に沿った都市空間の使い方をする市民に対しては、手厚いサポートを心掛けているとのことでした。
行政からは運営資金の拠出だけでなく、市職員1人のUDC2への出向が行われているそうです。市側のメリットとしては、例えば、市による駅前デッキ整備にあたりUDC2のデッキ活用の取組を引用し、「UDC2がニーズを明らかにしたのでデッキを整備する」というストーリーが作られているといいます。
さらには、合意形成のための会議体と、実行組織を分けることの重要性についても指摘がありました。