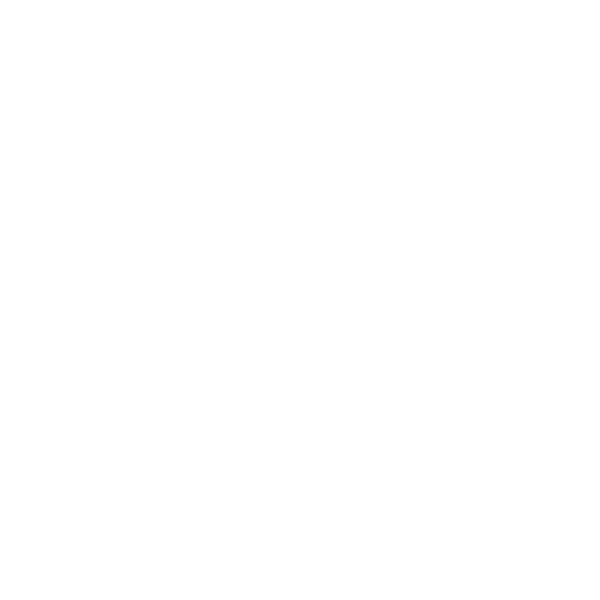編集後記・隅田川の将来像に向けて
今回の「すみだ川アートラウンド・ハブ」では、隅田川の水辺の活用を進めるための中間支援組織のあるべき姿について語られた計4回の検討会と、隅田川の水辺の活用が進んだ先に人々が求める将来像について語られた船上シンポジウム・ワークショップにより、隅田川の将来像に向けた具体的な検討が、理想と現実の両面から加速したように感じました。
学生時代に水辺空間を支える中間支援組織を研究テーマにしていたことをきっかけに今回の記事編集に携わらせていただいた私にとっても、本イベントは大変大きな学びとなりました。この場をお借りして感謝を申し上げます。
最後になりましたが、船上ワークショップの様々なアイディアに触発されて、隅田川の将来像に向けた妄想にも近い私案を述べさせていただき、編集後記を終わろうと存じます。
ドイツのエムシャー川は、以前は様々な工業排水が流れ込み、ルール工業地帯を象徴する存在でした。しかし1980年代にはルール地方の産業は衰退していき、「国際建築博覧会(IBA, Internationale Bauausstellungen)」という仕組みを用いて、産業構造の転換に直面した地域の新たなアイデンティティの構築が目指されました。エムシャー川沿いの広さ800平方キロに及ぶ地域で17都市が連携して117の都市・景観の再生プロジェクトを実施した「IBAエムシャーパーク」です。IBAエムシャーパーク公社はまさに中間支援組織のような動きをして、自身がプロジェクトオーナーとなるのではなく、州・国・EUの補助金を集め、調整・媒介・広報役として多くのプロジェクトを推進しました。
このIBAの考え方を隅田川の将来像に向けた検討に応用することは考えられるでしょうか?8か所の隅田川の防災船着場をそれぞれプロジェクトの拠点と考え、各拠点で日常に根差したつながりを丁寧に育てるとともに、それら全体をまとめて隅田川を東京の顔とするような大胆なコンセプトを提示することは可能でしょうか?隅田川全体を「沢山のプロジェクトが連動した展覧会の場」として捉えてみると、何だかわくわくしてきませんか?そのまとめ役として、中間支援組織が重要な役割を果たすような気がしてきませんか?そんな未来が近い将来やってくる気がしますし、やってきた際には私も何かの立場で参加したいと意気込むばかりです。
執筆:株式会社日建設計総合研究所/齋藤悠宇
東京大学大学院河川研究室にて水辺空間の活用における中間支援組織の役割について研究。現在は都市データの分析や都市政策の立案支援を仕事にしております。趣味はハッカソンに出ることです。