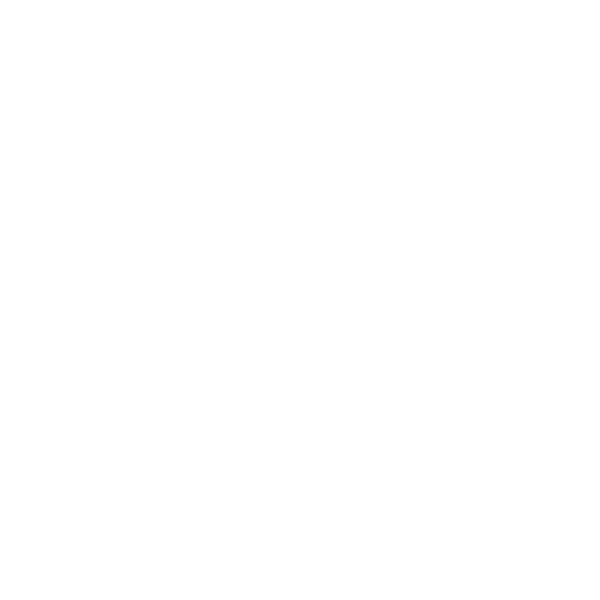ラウンドテーブル ARTs×SDGsの可能性をめぐる対話と実践
隅田川を舞台に展開するSDGsプロトタイピング
第三章:サーキュラー・リレーションシップ
「みんなのアートワークで『電気を生み出す屋台』がドレスアップ!」レポート

写真:高田洋三
はじめに
「すみだ川アートラウンド」は、ARTs×SDGsの可能性に着目し、隅田川流域の7区(北区・足立区・荒川区・墨田区・台東区・江東区・中央区)を活動領域とするアートNPO・団体が中核となり、他分野の民間事業者・行政関係者と対話を重ねることでアートの特性を活かした社会課題の解決を模索する事業です。
「ラウンドテーブル」「ハブ」「プラクティス」の3つの活動から構成される本事業ですが、ここでは流域の実践者たちの集う対話と実践の場である「ラウンドテーブル」の中でも、特に2024年度の活動に的を絞ってまとめましょう。
注:執筆者はすみだ川アートラウンド事務局のメンバーとして、ラウンドテーブルチームの活動に3年間関わってきました。以下、「私たち」という表現がよく登場しますが、これは事務局のラウンドテーブルチームのことを指しています。
▼これまでの活動
◯2022年度:サーキュラー・ダイアローグ
その前に、やはり少しだけ2022年度と2023年度のことについて振り返ります。
はじめ私たちは、SDGsにまつわるトピックとして「再生可能エネルギー」「食」「モビリティ」の3つの分野に着目しました。それぞれのテーマにおいて隅田川流域ですでに活動を始めている実践者、そしてアートとSDGsの連携に少し心惹かれる公募参加者に、アーティストと東京藝術大学の学生とが加わって、車座(ラウンドテーブル)になってお互いの活動を紹介しあい、関心を共有し、課題への次なる一手を自由にブレインストーミングしあったのが2022年度でした。
◯2023年度:サーキュラー・ガバナンス
初年度が準備編であったとすれば、2年目はいよいよ隅田川に飛び出した実践編の始まりと言えます。東京藝術大学で教鞭をとる岩間賢先生の屋台というアイデアをもとに、千葉大学の原寛道先生、そして墨田区で金属加工を手がける浜野製作所の協力が加わって作ることになったのが、車輪で運べて、屋根に配したソーラーパネルから電気を供給できる「給電できる移動式屋台」でした。上流は東京都北区の岩淵水門手前から下流は東京湾もほど近い築地大橋まで約36kmに渡る親水施設「隅田川テラス」の利活用を推し進めるイベント「すみだがわオープンテラス」(主催:公益財団法人東京都公園協会)と連携して場の提供を受けながら、公募参加者と力を合わせながら6回にわたる公開製作の末に屋台が完成しました。
リンク:2023年度レポ 電気を生み出す屋台をつくろう!
▼2024年度:サーキュラー・リレーションシップ
①「すみだがわオープンテラス 2024 with 宮前公園」、「すみだがわオープンテラス 2024 with あらかわ遊園」
気づけばあっという間に事業の最終年度。前年度に公募参加者とスタッフとで屋台を作り上げた時間を懐かしく感じながらも、いよいよそれを実際に活用するステップとなりました。作っている最中には、電気でお湯を沸かしてコーヒースタンドにしてはどうか、スマートフォンを充電できるスポットにしてはどうか、といくつかのアイデアが出たと記憶していますが、果たしてARTs×SDGsにふさわしい、そしてたくさんの人に親しんでもらえる屋台の活用方法とは一体なんなのか…。
そこで私たちが相談を持ちかけたのが、東京藝術大学の油画科を卒業し、画家・イラストレーターとして活躍するアーティストの新井友梨さんでした。新井さんは小学校の図工の先生という顔も持ち合わせる人物で、彼女と話し合いを重ねた結果、隅田川のそばに暮らす子どもたちを眼差した活動を行うことにまとまりました。つまり、彼ら/彼女らにこの屋台を自由な創作のアトリエとして使ってもらうこと、名付けて「移動式工作室」です。
そこで、昨年度に引き続き公益財団法人東京都公園協会と連携し、流域各所で開かれる「すみだがわオープンテラス」の一角で、新井さんとともにこの「工作室」を連続的に開催することとなったのです。
第1回の舞台は、10月19日から20日にかけて同時開催(「移動式工作室」は10月19日のみ参加)された「すみだがわオープンテラス 2024 with 宮前公園」、「すみだがわオープンテラス 2024 with あらかわ遊園」でした。
10月も下旬に差し掛かろうという日にしてはばかに暖かでした。私たちは東京都荒川区の宮前公園正面の隅田川テラスの一角に陣取り、「移動式工作室」をオープンしました。この日の内容は、ソフトボール大の小さな提灯に色とりどりのちぎり紙を貼り付け、オリジナルの照明を作って屋台を彩るというものでした。
この日の「オープンテラス」は堤防を挟んだすぐそこの宮前公園で開かれていた「宮前そらのマルシェ」というイベントと相乗りしたもので、そちらは数十軒の飲食・物販の屋台が軒を連ねる賑やかな催しでしたが、堤防が視覚的にも心理的にも双方のイベントを分断してしまっていて、果たして私たちのところに参加者は来るのだろうかと少しだけ不安な幕開けとなりました。
しかし、そこは休日の隅田川の川べり。ジョギングや散歩を楽しむ人の往来があり、またマルシェから足を伸ばしてきた来場者によって、次第に「オープンテラス」はイベント然としていきました。見たことのない形の屋台で見たことのないワークショップが開催されている様子に、ある人は通り過ぎざまに、またある人は歩みを止め、私たちの活動を不思議そうに眺めます。そうしているうちに、何人かの子どもたちが「移動式工作室」に参加してくれました。用意されたいろ紙の中から、子どもたちは思い思いの色を選び、好きな形に千切って提灯に貼り付けます。幼稚園くらいの子どもでしょうか、隣に座ったお母さんに忙しそうに話しかけながら提灯を彩っていきます。中学生どうしで連れ添ってきた際には、この年齢でも楽しめるかという懸念もどこへやら、アーティストの新井さんと取り留めのない穏やかなおしゃべりをしながら、ゆるやかにマイ提灯を作り上げていきます。

夕暮れも見えてきた午後4時すぎ、私たちは屋台をガラガラと押して、あらかわ遊園前のテラスへと移動しました。本当のところ、提灯を何十個もぶら下げ、いよいよ「これは何だ」という周囲の目を集めながらの移動を目論んでいたのですが、あいにくの雨天予報で、ブルーシートにくるんだ状態となり、少し残念でした。
移動には30分くらいかかったでしょうか。幸いにして雨には降られず、着いた先は荒川区西尾久、この日はドイツビールの祭典オクトーバーフェストになぞらえたその名も「オグトーバーフェスト2024 秋のビアガーデンin あらかわ遊園」が開催されている遊園地前のテラスです。どこか懐かしい雰囲気の観覧車の眼下に広がるこちらの会場、ビアガーデンを満喫した人たちが古代ギリシアのオルケストラよろしく形作られた半円形の石の段々に座ってひと休みしています。着いた頃にはあたりはうす暗がりとなっていました。しかし、提灯を携えてやってきた私たちにとって、これはまたとない好条件です。ソーラーパネルに繋がれ日中の陽の光を蓄えたバッテリーと、豆粒のような電球と、作った提灯とを一つひとつ繋いで、スイッチを入れると、たそがれどきの隅田川テラスに柔らかな提灯のあかりが灯りました。
点灯するといよいよ可愛らしく、通りすがりの大人も私たちに話しかけてくれます。「綺麗ですね。これは何ですか?」「昼間、子どもたちが提灯に飾り付けをしてくれたものです。」
アートでSDGsを考えるラウンドテーブル、3年目にして出現したのは、ソーラーパネルの電気を用いて隅田川に子どもたちの表現の場を作った「移動式工作室」でした。「給電できる移動式屋台」の活用方法の一つとして、まずは上々だったのではないでしょうか。

②すみだがわオープンテラス 2025 with 隅田川マルシェ
レッジョ・エミリア。これはイタリア北部の地名ですが、教育の文脈で言った場合、主に乳幼児を対象とした、個性を尊重し、自立性や協調性を育むような特定の手法を指します。新井さんがこの手法に興味があると話してくれたのは、年の明けた2025年1月のことでした。
このメソッドを参考にラウンドテーブルの活動ができないだろうか。
私たちは早速、2月23日・24日に東京都足立区の新田さくら公園前の隅田川テラスで開催される「すみだがわオープンテラス 2025 with 隅田川マルシェ」で実践することにしました。内容の骨格は主に3つ。ひとつ目は、そしてこれが今回の活動の中心ですが、新田さくら公園の落ち葉や石ころを使ったフロッタージュ体験。葉脈や石の微妙なでこぼこをクレヨンの様々な色で写し取り、それらが屋台を彩ります。ふたつ目には、太陽光パネルから貯めた電気を使うワークとしてライトテーブルを使って様々なモノを照らし出す体験。ライトテーブルとは、絵のトレースをする際などに用いる光るボードのことです。みっつ目には、木製のボックスを思い思いの模様に装飾する体験。このボックスはこの日のために、足立区千住でオルタナティブスペースの運営を手がける方に特別に作ってもらったものです。全て書くと長くなりますから、この場はフロッタージュに絞って記述することにします。
開催初日は、さすがは川沿い、2月であることを考えてもひときわ冷たい風の吹きすさぶ日でした。それでも会場の新田さくら公園の周囲は幼稚園から小学校くらいの子どものいる世帯などが多く暮らすマンションの立ち並ぶ住宅街で、同時開催の「隅田川マルシェ」は多くの子ども連れの家族で賑わいます。「何やってるの?」「公園の葉っぱを使ってお絵描きをしているの。一緒にやってみよう?」公園に落ちている桜の葉やフウの実などから好きな素材を選び、クレヨンを選んで、早速フロッタージュに挑戦です。ところが、小さな子どもにとっては微妙な力加減が難しく、ぐりぐりと力任せに塗ってしまって上手にできないこともしばしば。それでも、葉脈の中央の芯のところなど凹凸のはっきりしている箇所をなぞっているうちに、だんだんとコツを掴んでいきます。「そう、それ!」「できた!もう一枚、もう一枚」。ほどなくして私たちの「移動式工作室」も多くの子どもたちで満席となりました。


写真:高田洋三
お父さんやお母さんと一緒になって取り組む子どもも多い中で、中には大人を公園や他のお店で遊ばせておいて、きょうだいや友達と連れ立って参加する子どもも何組かいます。気づけばそんな子どもたちは、別のグループの子どもとこの「移動式工作室」のなかで友達になっていました。「その色貸して」「ちょっと待って」「いつあそぶ?」「いま?」「いいよ」。レッジョ・エミリアは、大人の介入を極力排し、子どもたちだけでコミュニケーションをとることを通じて自立性や協調性を育むことを目指した方法で、通常1年程度の時間をかけて行う方法です。けれど、そんなタイムスパンをやすやすと超え、今できた友達と遊具の方へ向かって風のように駈けていくその背中がとても頼もしく私たちの目に映りました。
一方で、フロッタージュよりも、どちらかというと新井さんとのお喋りの方を大事そうにしている小学生くらいの子どももいます。間近に控えた転校について話しています。今いる学校では自分たちでクラブを新しく立ち上げられること、立ち上げたら1年間はそのクラブに所属しなければならないこと、転校先の学校には自分に合うクラブがあるか気がかりだということ。新井さんは、ひとつひとつ柔らかな相槌を打ちながら、その子どもの語りに耳を傾けていました。