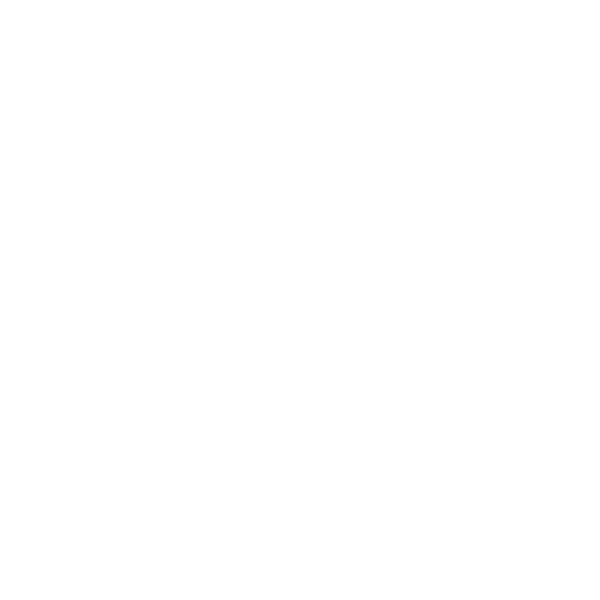すみだ川アートラウンド・プラクティス「子どもと地域」
座談会 開催レポート
ムジタンツはこれまで、約6年間にわたって足立区保木間地域での活動を続けてきました。
2024年11月、これまで中心となって連携いただいてきた方々や、全国各地の取り組みについて造詣の深い大澤寅雄さんをゲストにお招きし、「Meeting アラスミ!」(2019〜2021年度)から「すみだ川アートラウンド」(2022〜2024年度)へと続いてきた活動について語る座談会を開催しました。
当日は、これまでに実施してきたプロジェクト全体の変遷を概観し、事前に行ったムジタンツ事務局とアーティストとの振り返りの内容を共有した上で、それぞれの立場から感じてきたことや考えたことについてお話いただきました。
本レポートでは、座談会で交わされたディスカッションの内容の一部を抜粋してご紹介します。より詳細な内容は、今後研究論文や書籍として公開できるよう準備中です。
開催日
2024年11月26日(火)
場所
東京藝術大学 千住キャンパス
参加者
大山光子(一般社団法人 あだち子ども支援ネット 代表)
橋本久美子(母子生活支援施設 母子支援員)
保知巡(母子生活支援施設 少年指導員)
大澤寅雄(文化コモンズ研究所)
東京藝大 x みずほFG「アートとジェンダー」共同研究プロジェクトメンバー
熊倉純子(東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科長)
石川清隆、酒井雅代、山崎朋(ムジタンツ事務局)
■協働アーティストからのフィードバック
座談会に先駆け、「アートなお祭り」および「お祭り準備ワークショップ」に参加した協働アーティストと振り返りを行いました。そこで交わされた言葉より、一部抜粋してご紹介します。
大西健太郎(アーティスト/谷中のおかって):
- コミュニケーションの場だったと感じている。そう感じられたのは、大山さんの存在が大きい。その日出会った人、思いがけない人との出会いを色々なコミュニケーションの形の中で試してみたいと思った。
- 想像もできない人と出会うってどんな気持ちだろうということを考えた。それは母子生活支援施設の子どもたちとの(昨年度から継続した)関わりの中で考えていた。
- 嘘はつけないと思った。何か取り繕ったり、偽ったりはできない……今あるものだけでまっすぐ話してみろって言われている感じがした。
- 事前ワークショップで行った内容は、お互いの経験や認識の範疇におさまりきらない「出会い」の化学反応を起こそうとして考案したものだった。
寺内天心(東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科 学部4年):
- 母子生活支援施設での関わりは、ある種のエアロックのような機能を持ちうるもののように感じた。誰かと一緒に入って、とどまって、抜けていく、そんな「宇宙船」のようなエナジーを持つ可能性がある場所なんだと思った。
- ワークショップの場は、どうこうできることばかりじゃないということを思い出させてくれた。
- 行きたい/会いたい/一緒にやりたいという想いがどんどん重なっていった。
- 母子生活支援施設の職員の方とまだきちんと知り合えていないところを自身の課題として感じていた。
■連携する福祉スタッフからのフィードバック
連携先の福祉系職員の方々からは、個々人の所感として、本プロジェクトにおける意義や課題を共有いただきました。ここでは「参加した子どもたちに起きたこと」に焦点をあて、一部抜粋したものをご紹介します。
「本当にのびのびと表現されるアーティストさんたちと関わって、“のびのびと表現する”っていうものに触れられたっていうのは、強く感じるところでした。かつ、 特にムジタンツの身体全体を使って表現する動きもあって、お家に引きこもりがちな子たちにとっては、身体感覚に触れるすごくいい機会だったと思っています。」(母子生活支援施設少年指導員)
「この音楽は自分に合っているとか、ダンサーの方々に引き込まれて踊っちゃったよっていう、その自分の気づき。そういうので次の日目が覚めたときに自分が変われるっていう、なんかそんな変な面白さがあるんですよ、アートって。それを本当に積み上げてくれた。ムジタンツという名称がまだ理解はできてないと思うけど、でも面白いことを運んできてくれる 人たちという、親近感はすごく馴染んできた。」(一般社団法人 あだち子ども支援ネット 代表)
「(アーティストが)いっぱい関わってくれて、 子どもたちの気持ちとしたら、“見ててくれた”っていう、“あの人と目が合った”っていうことが、 ものすごく自信につながってるんですよね。だから、参加してくる。 ただただ面白いとかいうより、あの人が見ててくれて褒めてくれたっていうのが、ひとつひとつの自信になる。」(一般社団法人 あだち子ども支援ネット代表)
■東京藝大 x みずほFG「アートとジェンダー」共同研究プロジェクトのメンバーからのフィードバック
〈みずほ〉の一部のメンバーの方には「アートなお祭り」にもご参加いただきました。お祭りに参加された方からは、お祭りの場で出会った子どもたちとのやりとりや様子について感想をお聞きしました。ここでは、みずほ社員の方から見た本プロジェクトについて、いただいたコメントの一部をご紹介します。
「この活動を通じて生まれた絆をそのまま終わらせるのはもったいないと感じ、これからもこの関係を繋いでいきたいと思うと同時に、中途半端な気持ちで関わるべきではないとも考えています。今後もぜひ継続して関わっていきたいと感じます。」(20代社員)
「企業人として働く中で何ができるのか考えていきたいという思いが、この活動に参加させていただく中でより強く芽生えました。今は私たちに何が出来るのかは模索中ではありますが、関わっていく中で何かお役に立てたらいいなと思っています。」(20代社員)
「地域に繋がることのできるコミュニケーションの「媒体」になっているのと同時に、アーティストの方にとっては自らのアートとしっかりと向き合えるような新しい環境を提供する場になっていたのかなと勝手に想像しました。場づくりではなく助成というかたちではありましたが、 サポートできて良かったなと思いました。」(30代社員)
「アートなお祭り」に至るまでの全てのプロジェクトは、福祉領域スタッフの方々との対話の先に具現化されたものでした。そのプロセスにおいては、困難が生じる場面もありましたが、福祉領域の方々の主体的な参画があったからこそ継続できたプロジェクトでした。
座談会の場においても、制度化された福祉領域とアートが連携するときに生じる課題について議論がなされました。特に、母子生活支援施設において本プロジェクトをどのように位置付けるかという点に関しては、子どもの参画、子どもの家庭環境、福祉施設職員の勤務体制、職務責任といった重層的な課題が含まれていることも詳らかになりました。座談会の場で大澤寅雄さんが「自由が担保できるフレームを作るということなんでしょうか」と述べていたとおり、福祉側、アート側、お互いが窮屈にならずに連携を継続する「フレーム作り」を、これからも対話を継続しながら更新させてゆく必要があると感じました。
今後、本プロジェクトを継続させてゆく上で、プロジェクトの事業評価という観点から大澤寅雄さんより以下のコメントをいただきました。
「例えば説明しやすいのは、“参加者が90人”。このように継続してきた中で、当初はすごく少数だったのが、こんなに増えましたというのは、評価的に説明がしやすいわけですけど、 その90人の中で本当に来てほしい子が何人いてとか、こちらが想定はしてなかったけどこういう属性の子が何人来ててとか、 本当に来てほしかったけど来れなかった子が何人いてっていうところは、検証してみるとすごく大事なポイントかなという気もしますよね。90人という数字以上に、これ結構大事かもしれないなと思います。」
座談会での熊倉教授の言葉を借りれば「きちんと対話をして、もしかしたら福祉の制度に欠けているものを一緒に作り出すようなことは、本当に福祉側にも負担が大きい。双方よく考えていかなきゃいけないという時代がやっと始まったところ」であり、座談会の場でそれぞれの立場から見えた意義や課題について言語化がなされたことは、福祉領域と連携するアートプロジェクトを更新していく上で貴重なドキュメントとなりました。本座談会の内容については、今後、研究論文・書籍として出版する準備を進めています。福祉領域でアート活動を取り入れたいと思っていらっしゃる方や、福祉領域と連携した活動を展開してみたいと思っているアーティストの方々の一助となればさいわいです。
最後に、大澤寅雄さんからいただいたコメントを抜粋してご紹介します。
「みずほFGの企業理念である 『変化の穂先であれ』というバリューの言葉がいい言葉だと思って。今やっていることは本当、小さな穂先に現れている状況、このようにアーティストが関わることで変化が見えてきている状況だから、この穂先の部分をずっと見続けてほしい。みずほさんならではの視点での関わり、支援の在り方は変化していくかもしれないですけど、この変化の穂先は大事だと。これを社会全体の実りにどうつなげていくかということを観察したいですね。」
文・編集:酒井雅代・山崎朋
写真:中川周